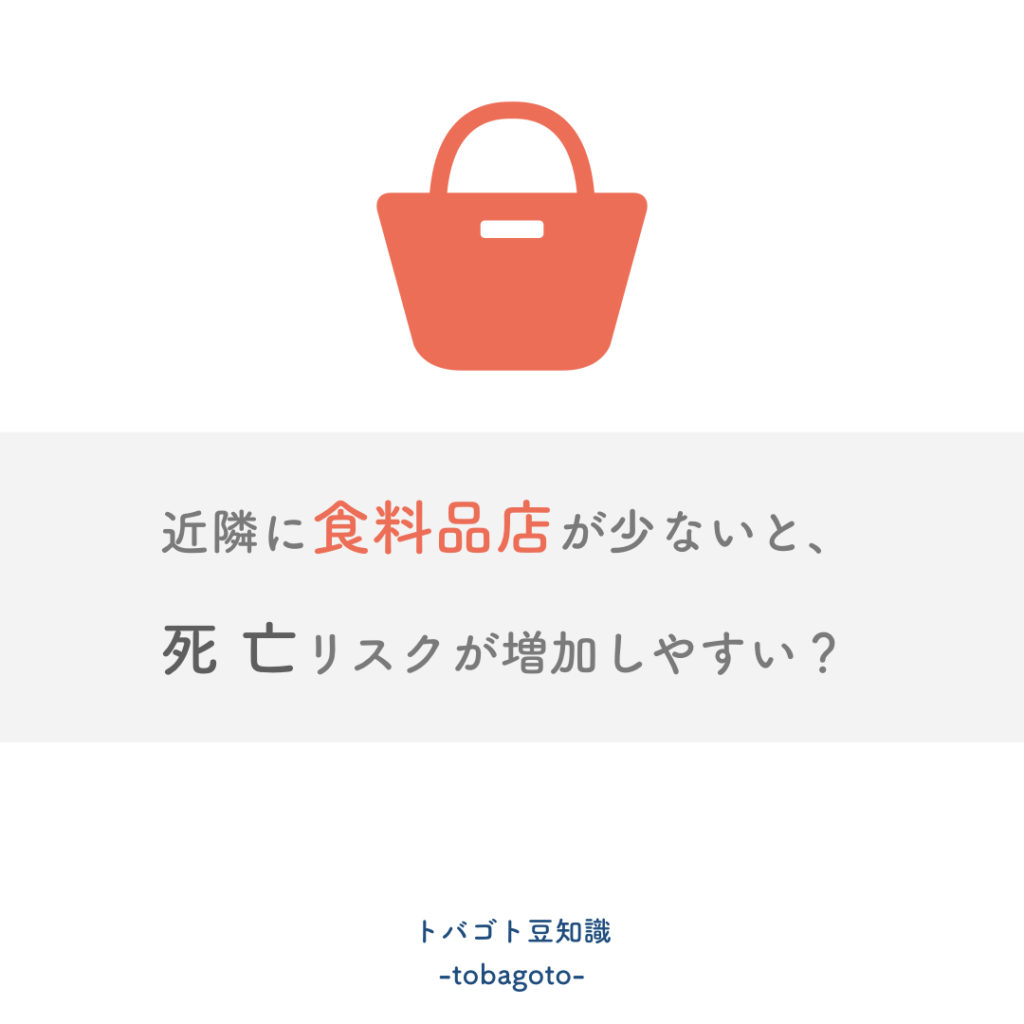
生活する地域に食料品を買えるお店がある。これは、その地域にとって物凄く重要な社会資源です。
鳥羽市で、食料品店を経営してくれている方々、本当にありがとうございます。
もちろん、お店がなく、食べ物を買うことが出来なければ、生活が困難になるので「不便だ!」と思うのは当然です。
でも、それだけでは済まないのかもしれない。というのが今回のお話になります。
「日本の高齢者における近隣の食料品環境と死亡リスク」を調査した研究です。
この研究では、65歳以上の日本人高齢者49,511人を約3年間追跡し、その高齢者宅の近隣にある「野菜や果物が手に入る食料品店の数」と「死亡リスク」の関係を調査しています。
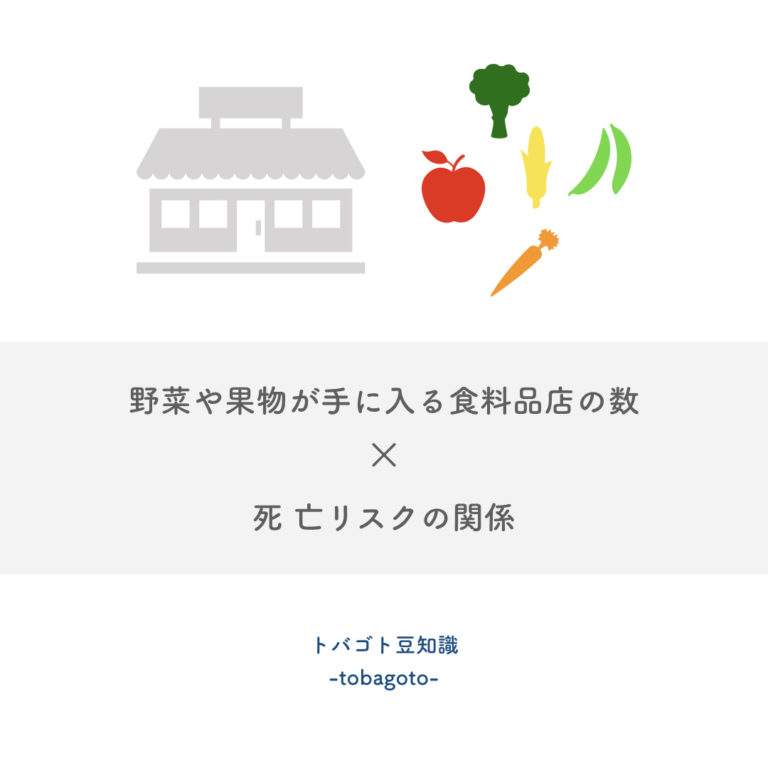
その結果、
外出時に車を利用することのない高齢者で、近隣に食料品店の選択肢が少なかった方の場合、死亡リスクが高くなっていた、とのことです。
つまり、地域にお店があることは、生活の不便性を解決するだけでなく、死亡リスクにも関係があったのです。
ちょっと怖いですよね。
ということは、今あるお店は絶対に失くしてはならない!のです。
でも、食料品店の存続って、食料品店だけの企業努力だけでは難しいことが沢山。
人口が減れば、お客さんは自然に減ってしまう。そうすると、経営が厳しくなって、お店を存続していくことが難しくなるのは当然です。また、お店を経営してくれている方も次第に高齢化していくことは予想できます・・・
それなら、鳥羽を訪れる観光客がもっと増えれば、経営は楽になるのでは?
もっと魅力的な鳥羽になれば、お店を開きたい人も増えるのでは?
だから、行政なんとかしてよ!
うーん、これだけでは正直厳しいですよ。行政だけが奮闘しても限界があります。
「その地域で暮らす一人ひとりの住民が、そのお店で商品を買う」
それがまず、お店の存続につながり、地域の利便性の維持につながり、自分自身の健康にもつながる。めぐり巡って、自分や地域に帰ってくる。
こうやって、登場人物みんなが協力すれば、よい結果も見えてくる可能性があります。
まさに、最近、鳥羽市でよく聞く言葉「地域共生社会」ということになりますね。
たいせつなのは、いつも「他人ごとではなく、自分ごと」と思うことです。
さいごに、鳥羽市で食料品店を経営している方々、もしかしたら、知らず知らずのうちに、物凄い「福祉」を実践していたのかもしれません。いえ、すでに「福祉」を実践しています!今後ともよろしくお願いいたします。
記載日:令和元年5月15日